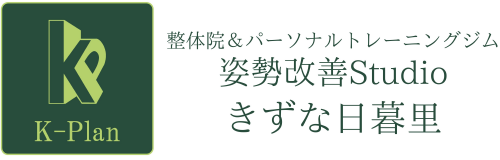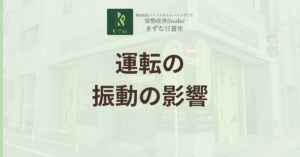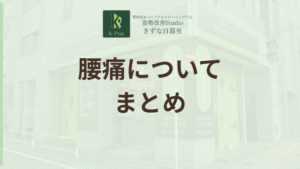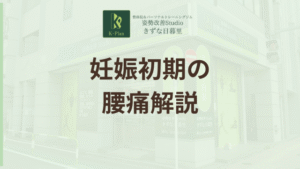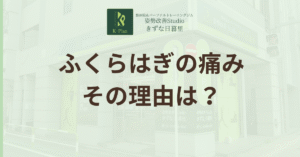年齢を重ねると、なんとなく腰が痛い、動くのがおっくう…そんな感覚が増えていきます。
でも、「年だから仕方ない」とあきらめてしまうのは、少しもったいないかもしれません。
実は、腰痛の原因は“年のせい”だけではなく、日々の体の使い方や習慣が深く関係しています。
この記事では、高齢者に多い腰痛の特徴と、少しずつ体が動きやすくなるヒントをお伝えします。
「年のせい」だけじゃない?高齢者の腰痛に多い3つの誤解
①「体が硬いのは年齢だから仕方ない」って本当?
動かさないことが柔軟性を奪う
年齢を重ねると体が硬くなる、というのは半分正解で半分誤解です。
本当の理由は、年齢ではなく“動かさなくなったこと”にあります。
体は使わないほど固まり、使うほど柔らかさを取り戻します。
何歳からでも、動かし続ければ柔軟性はちゃんと戻ってきます。
少しずつ動かすだけでも体は変わる
急に無理なストレッチをする必要はありません。
まずは朝起きたときに手を伸ばす、寝る前に足首を回すなどの小さな習慣から始めましょう。
「気づいたときに少し動かす」ことだけでも、体は徐々にほぐれていきます。
▶身体を柔らかくする方法とは?ストレッチ以外で柔軟性を高める意外なコツ
②「歩けないのは筋力がないから」って思っていませんか?
必要なのは“筋力”よりも“筋持久力”
重いものを持つ力よりも、「長く動き続ける力」のほうが高齢者には重要です。
階段を1段上がるより、10分歩くほうがつらいと感じるなら、筋持久力が落ちているサインです。
階段1段を登れる、立ち上がれるということは、最低限の筋力はすでに備わっている証拠です。
にもかかわらずすぐに疲れるのは、動き続ける力=“持久力”の不足が背景にあります。
息切れや足のだるさは、持久力不足の影響が大きい傾向にあります。
バランスが崩れると、動きが怖くなる
もうひとつ大きな要因が「バランス能力の低下」です。
まっすぐ立つ、足を一歩前に出す、それだけでも不安定に感じることがあります。
高齢者に多い特徴のひとつに、「歩幅が狭くなる」「歩くテンポが速くなる(歩数が増える)」という変化があります。
これは、ふらつきを避けようとする無意識の反応で、足を小刻みに動かすことで転倒リスクを減らそうとしているからです。
体のブレが大きくなると、“早く足をつかないと倒れてしまいそう”という不安が働きます。
その結果、歩幅は狭くなり、テンポは速くなるという傾向が出てきます。
こうした動きの変化は、バランス感覚の低下と密接に関係しています。
そして不安からさらに動かなくなり、バランス能力も持久力も落ちるという悪循環につながります。
バランス能力→コントロール力について簡単に触れています。
▶ピラティスとヨガ・筋トレの違いがスッキリ!次の一歩は“機能改善トレーニング”
③「昔から姿勢が悪いから腰痛になる」は半分正解
姿勢のクセは蓄積する
猫背や反り腰といったクセは、日々の使い方の積み重ねで定着します。
そしてそのまま固まってしまうと、腰にかかる負担も大きくなります。
「正しい姿勢」に戻すには、意識して使い方を変えることが必要です。
でも変えられる“使い方の意識”もある
背すじをただ伸ばすのではなく、「どう使うと楽に動けるか」を意識することが大切です。
姿勢は“形”ではなく、“使い方”と考えてみましょう。
座る・立つ・歩くなど、よく行う動作の中でこそ、意識を変えるチャンスがあります。
▶「良い姿勢はつくるもの」──無意識を味方にする3ステップ意識トレーニング
高齢者の腰痛に多い特徴とは?
加齢で変わる体の仕組みと痛みの出かた
筋肉や関節の動きは、年齢とともに少しずつ変わっていきます。
特に背骨の柔軟性や股関節の動きが悪くなりやすく、腰をかばう姿勢が習慣化しやすくなります。
また、神経の伝達が鈍くなることで痛みへの反応も変化し、違和感やだるさとして現れることもあります。
病気が隠れていることもある?
高齢者の腰痛には、圧迫骨折・脊柱管狭窄症・腎臓疾患など、疾患が関係していることもあります。
「痛みが強いまま続く」「夜中に痛くて起きる」「脚にしびれがある」などの症状があれば注意が必要です。
気になる症状があれば、医療機関の受診を検討してください。
「もう動かないとダメ」腰痛を改善するための習慣づくり
柔軟性は“使いながら”取り戻せる
体を柔らかくするには、静かに伸ばすストレッチだけではなく、“動かしながら”柔軟性を育てることが重要です。
おすすめは「寝ながら膝を立てる」「肩甲骨を寄せて戻す」「左右にゴロンと寝返る」など。
動きの中でほぐすことが、実は一番自然で無理のない方法です。
歩くために必要な筋持久力とバランス感覚
歩き続けるには、下半身の筋肉と、ぐらつかない体幹の両方が必要です。
高齢者におすすめの基本トレーニングが「片足立ち」です。
【片足立ちトレーニングのやり方】
- 転倒しても安全な場所、手すりや壁の前で行う
- 片足を軽く浮かせ、10〜60秒キープ
- 左右交互に1日3セットを目安に行う
この運動は、体幹の感覚を呼び起こし、姿勢保持にもつながります。
デイサービスや介護施設などでも効果が確認されている安全な方法です。
さらに姿勢も意識したバランストレーニングはこちら
▶前重心が不調のもと?『かかと重心』で姿勢改善&腰痛予防を目指そう!
※転倒には充分に注意してください。
姿勢を「整える」のではなく「使う」意識へ
背すじをピンと伸ばしても、すぐに疲れてしまうようであれば、それは“形だけ”の姿勢です。
本来は、無理なく動ける位置に体が整っていることが大切です。
「お腹に少し力を入れる」「骨盤を立てて座る」「背中を反らしすぎない」など、
小さな意識の積み重ねが“使える姿勢”をつくります。
楽して治す?努力して整える?そのバランスが大事
体に“まかせる”のか“整える”のか
湿布やマッサージ、コルセットなどは、“体を楽にする手段”として有効です。
痛みが和らぐ、安心できるという意味では、どれも必要な選択肢といえます。
ただ、それだけでは腰痛の根本的な改善にはつながりにくいのも事実です。
体を整えていくためには、やはり“自分で動かすこと”が欠かせません。
もちろん、使って楽になるのであれば、道具を上手に活用すること自体は何も問題ありません。
大切なのは、それに“頼りきり”にならず、少しずつでも「自分の体を整える習慣」を持つことです。
小さな努力が、痛みのない毎日につながる
最初は5秒でもいい、まずは体に刺激を入れることがスタートです。
「動かす→慣れる→疲れにくくなる」という変化が、少しずつ腰の状態を安定させてくれます。
毎日の小さな積み重ねが、未来の「痛くない体」をつくっていきます。
まとめ
- 柔軟性の低下は“年齢”ではなく“使わなくなったこと”が主な原因
関節や筋肉は動かす頻度によって柔らかさを保つため、日々の動作の減少が硬さを招いているケースが多く見られます。 - 歩けなくなるのは筋力不足ではなく“筋持久力とバランス能力の低下”が主な要因
長く動く力と安定して動く力が落ちることで、転倒や疲労を感じやすくなります。歩かないことでさらに悪化する悪循環が起こります。 - 体幹姿勢の崩れは歩行の効率や安定性に大きく関わる
体幹の前傾や姿勢のクセが、バランスの取りづらさや腰の負担を増やすことが示されています。
出典:佐藤信『高齢者における体幹姿勢が歩行動作の力学的エネルギー利用の有効性に及ぼす影響』日本バイオメカニクス学会(2015)
柔軟性やバランスは年齢に関係なく、使い方次第で十分に取り戻せます。
大切なのは「年だから」ではなく「動いてないから」と視点を変えることです。
「疲れるのは嫌だ。」わかります。
しかし、少しだけ疲れるような習慣が、将来の健康寿命を支えてくれる大きな力になります。
難しいことはしなくても構いません。
まずは毎日5秒から、腰にやさしい動きを取り入れてみましょう。
万が一、起き上がれないときの対処法と医療機関にいくべきかの判断基準を解説しています。
▶高齢者が腰痛で起き上がれないときの対処法 今すぐできる応急処置と再発予防
腰痛についてこちらで詳しくまとめています。
▶腰痛の原因・対策・予防法まとめ!セルフケアから生活改善まで徹底解説!